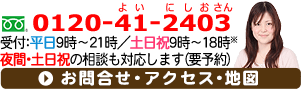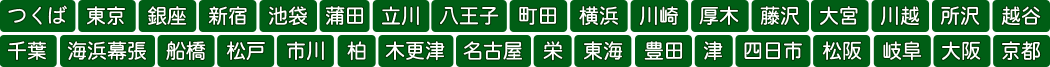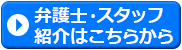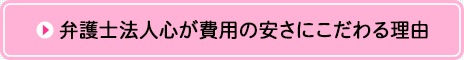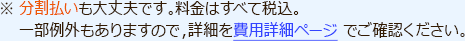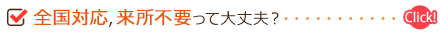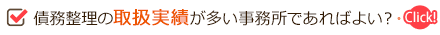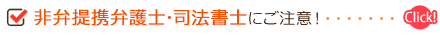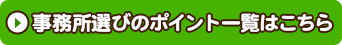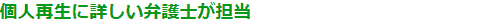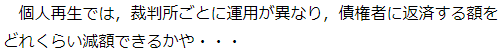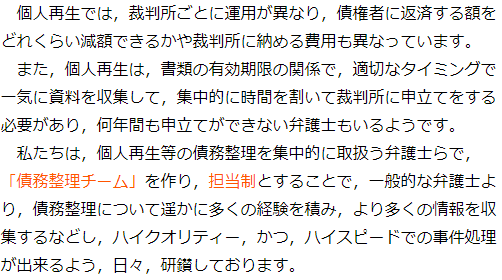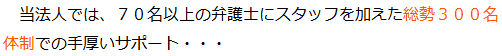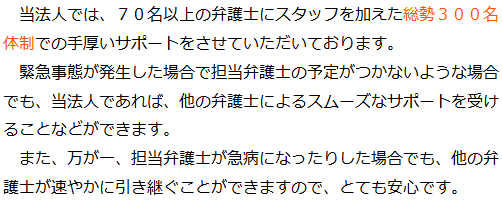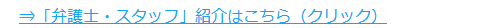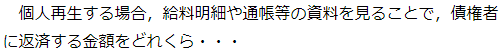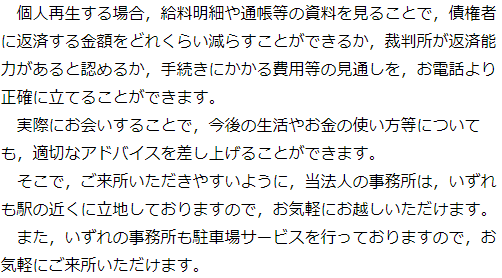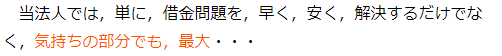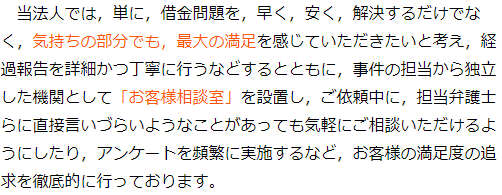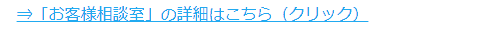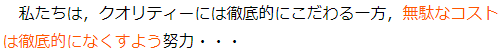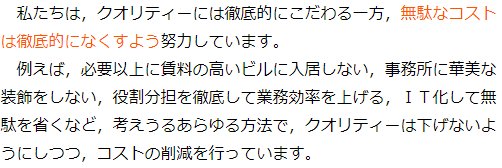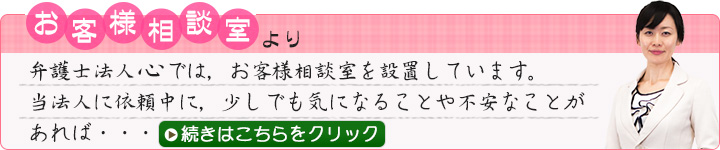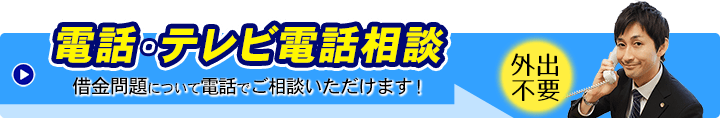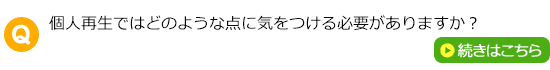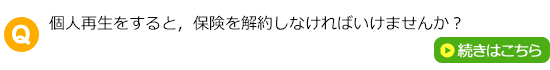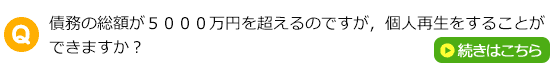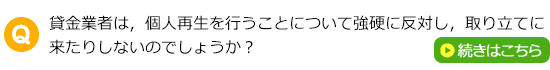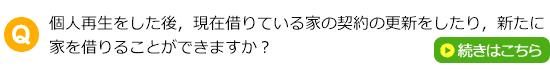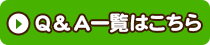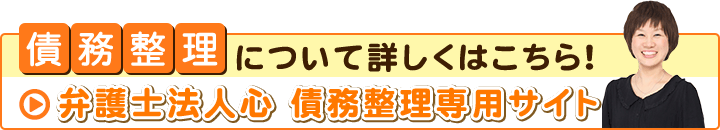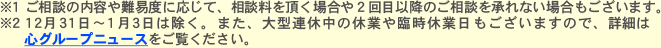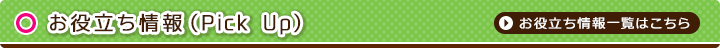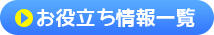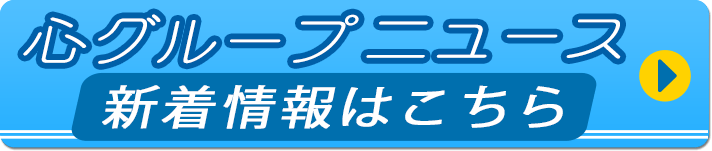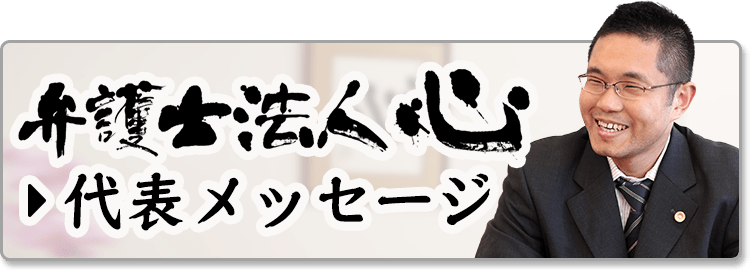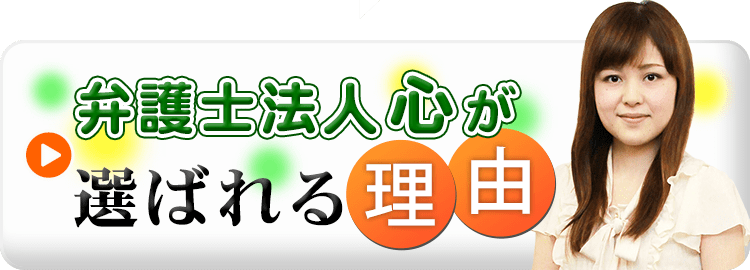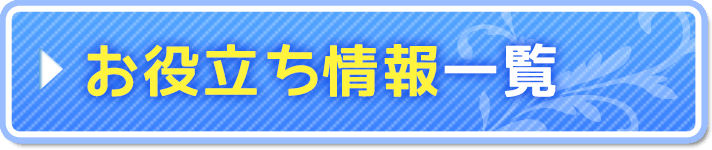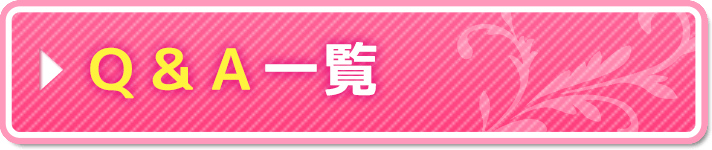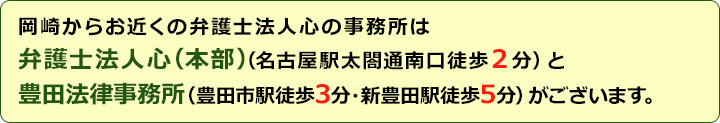
ご利用いただきやすい場所にあります
当法人の事務所は駅の近くに設けているため,公共交通機関を用いてお越しいただきやすいかと思います。お気軽にご相談ください。
個人再生を行うことが効果的ではないのはどのような場合か
1 個人再生が効果を発揮しにくいケースがある

個人再生とは、裁判所の手続きによって、借金の総額を減額したうえで、それを分割で支払っていく手続きです。
個人再生が上手く進めば、借金を1/5等の大幅な割合でカットした上で、3年から5年程度の期間で分割返済することが認められますので、返済しきれないほど多額の借金を抱えてしまったけれども、自己破産だけは避けたいというような方にとって、非常に効果的な選択肢の一つとなっております。
しかし、中には個人再生があまり効果を発揮しにくい類型の事案もあります。
2 借金の総額が少ない場合
個人再生の場合の最低弁済額は100万円となっています。
そのため、たとえば、借金の総額が80万や120万ぐらいの方の場合、「借金の総額を減らす」という個人再生手続きのメリットが、まったくないか、僅かしかないことになってしまいます。
3 一部の債権者に借金が集中している場合
また、一部の債権者が過半数以上の債権額を有している場合には、その債権者に反対をされてしまうと、小規模個人再生手続きをとることができなくなってしまう点で、不確実性を伴うことになります。
この場合でも、債権者の同意が必要ない給与所得者等再生手続きによる個人再生は可能ですが、月々の返済額は、一般的に、小規模個人再生手続きの場合に比べると高くなりやすいです。
4 財産がたくさんある方
また、個人再生手続きには清算価値保障原則というものがあります。
これは、個人再生をしたことで、破産をした場合にくらべて債権者が損をしてはいけないというルールです。
そのため、財産がある方の場合、個人再生の手続きであっても、「破産したらこのくらいは換金できるだろう」という金額までは、返済をしなければならないことになります。
例えば、借金が500万円ある方が、預貯金等の破産の際に配当対象となる財産を300万円持っていた場合、小規模個人再生手続きの最低弁済額は100万円になりますが、300万円までは分割返済しなければならないこととなります。
持っている財産が、預貯金や生命保険の解約返戻金等の、現金化が容易な財産であれば、それらを計画返済の原資にすれば済むので、大きな支障はないのですが、例えば、住宅ローンを完済していたり、完済まであと少しの自宅不動産がある場合や、相続によって遠方の田舎の田畑を相続した場合など、現金化が簡単でない財産を持っている場合には、現金が用意できないのに返済しなければならない金額だけが増えてしまい、個人再生の手続きが進められなくなってしまうおそれがあります。
5 適切な方法を選択するためにもご相談ください
このように、個人再生の手続きは、上手く進めば非常にメリットの大きな制度ですが、選択するにあたって考慮しなければならないこともたくさん存在しています。
適切な手続きを選択するには、弁護士等との事前の打ち合わせが必要不可欠であると考えますので、岡崎にお住まいで個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。
給料の差押えが心配な方へ
1 個人再生と給料の差押えについて

債務整理のご相談に来られる方の中には、すでに長期間にわたって滞納が続き、その結果債権者によって給料を差し押さえられている方もいらっしゃいます。
また、相談に来られた段階では、給料は差し押さえられていなかったものの、申立ての準備を進めている間に、給料の差押えがされてしまう場合もあります。
一度、給料の差押えをされてしまうと、手取りの収入額が大きく減少するため、個人再生を進める上で必要となる、弁護士費用や実費などの積立てが困難となってしまいます。
2 給料の差押えが中止されるタイミング
では、給料の差押えに対して、どのような対応方法があるのでしょうか。
個人再生の方針で進めているのであれば、できるだけ早く裁判所に対して個人再生の手続き開始を申し立てるというのが、もっとも分かりやすい対応方法になります。
民事再生法39条1項では、「再生手続開始の決定があったときは・・・再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等・・・・の申立てはすることができず、破産手続、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続・・・・は中止」すると定められています。
なお、これは、あくまで個人再生の手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合の話ですので、裁判所に申立書を提出しただけでは、すぐに「中止」が認められるわけではありません。
そのため、申立てから開始決定までの間に強制執行が行われる可能性はあります。
そうした強制執行を止めようと思った場合には、民事再生法26条1項2号にもとづく強制執行手続き中止命令の申立てや、同法27条の強制執行等の包括的禁止命令などの方法を、別途とる必要があります。
3 強制執行の中止後の給料はどうなるのか
なお、個人再生手続きの開始決定がなされて強制執行の中止が認められた場合でも、すぐに元通りの給料を受け取ることができるようになるわけではありません。
あくまで、法的な効果としては「中止」であるため、いつ再開されるか分からないと判断されるからです。
そのため、強制執行が中止された以降の給料を、実際に受け取るには、給料差押えの効力が失われるのを待つ必要があります。
具体的には、民事再生法184条に「再生計画認可の決定が確定したときは、第三十九条第一項の規定により中止した手続又は処分は、その効力を失う。ただし、同条第二項の規定により続行された手続又は処分については、この限りでない。」と書かれているように、個人再生の手続きを進めていき、再生計画の認可決定を得るのを待たなければなりません。
4 差押えを受ける前にお早めにご相談ください
このように、給料差押えを受けた場合、個人再生の手続きを進めることで解決はできるものの、実際に、給料を元通り受け取れるようになるには相当の期間を要します。
できることならば、給料の差押えを受けることなく、個人再生の手続きを終えることができるのが、もっともスムーズな解決といえます。
そのため、借金の返済にお悩みの方は、長期滞納等に陥る前にできるだけ早めに弁護士にご相談いただくとよいかと思います。
岡崎やその周辺にお住まいで個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。
小規模個人再生が認められた場合の返済額について
1 個人再生という手続き

個人再生とは、裁判所の手続きを通して借金を減額し、その減額後の借金を3年から5年かけて分割して返済していく手続きです。
ここで、債務者の方がもっとも気になることが、「この手続きが成功した場合、実際にどの程度、借金が減額されるのか?」という点ではないかと思います。
2 小規模個人再生手続きの最低弁済額
個人再生の手続きのうち、小規模個人再生手続きを選択した場合、その手続きを行うことによって、どのように借金が減額されるかについては、以下のとおり、明確に決まっています。

このように、総債務額の金額に合わせて、例えば500万円までならば100万円、800万円の方なら5分の1の160万円というように、法律上の最低弁済額の決まりが存在しています。
そのため、もし、自分自身の債務額が全部でいくらか把握できているのであれば、上記の表を参考に目安を立てていただくとよいかと思います。
3 1か月あたりの返済額について
また、総額が上記の表のように減額されたとして、実際の1か月あたりの返済額がどうなるのかも重要です。
返済については、原則として3年、例外的な事情がある場合には5年間の分割払いが認められています。
実際には、3か月に1回の支払いなどに設定することが多いですが、1か月あたりで計算するのであれば、最低弁済額を36回(3年)または60回(5年)で割った数が、1か月あたりの返済額となる計算です。
この金額と、ご自身の収入から生活費等を引いて手元に残せそうな金額を比較して、後者の方が大きければ、個人再生をする価値があるといえます。
4 弁護士へご相談ください
このように、個人再生がうまくいけば、借金を大幅に減額して返済をすることができます。
ただし、実際には、債権者の反対に遭い、思っていたように事が運ばなかったり、あるいは、所有する財産が高額で評価されたため、最低弁済額以上の返済を求められたりするといったことも起こり得ます。
具体的な事件の見通しなどについては、まずは当法人の個人再生を得意とする弁護士までお気軽にご相談ください。
お客様からのご相談をお待ちしております。
自宅をお持ちで個人再生をお考えの方へ
1 個人再生と住宅ローン

個人再生という手続きは、裁判所を利用して、借金の総額を法律の定めに従って減額してもらい、減額された借金額を3年から5年かけて分割で返済していくという手続きです。
このように、個人再生は、債権者に対し法律に基づいて債権カットを求めていく手続きであるため、原則として一部の債権者がひいきされるようなことがあってはならず、すべての債権者が公平かつ平等に債権カットの負担を受けなければならないと考えられています。
そのため、個人再生をすると決めた場合には、一部の債権者にだけ返済を続けたりすることは、原則として認められません。
もっとも、この原則を徹底するとなると、住宅ローンの返済も当初の契約どおりには継続できなくなるため、個人再生をしようとすると、住宅ローンの期限の利益が失われます。
そうなると、住宅につけられた抵当権が実行されて、自宅を失うという結果になってしまいます。
2 個人再生の手続きを行っても自宅を残す方法
そこで、これでは住宅ローンを抱えた個人の方がなかなか個人再生に踏みきれないということで、民事再生法196条以下に「住宅資金貸付債権に関する特則」というものが設けられています。
これは簡単にいうと、この「住宅資金貸付債権に関する特則」に定められている要件を満たしている場合には、例外的に、住宅ローンだけは当初の契約どおり返済を継続することを認めるということです。
例えば、債務者が自分の居住する建物とその建物のための土地等を手に入れるために負担した住宅ローンで、その土地と建物に抵当権がついている場合には、個人再生の手続きを行っても住宅ローンの返済を継続して自宅を残すことができる可能性があります。
3 自宅をお持ちで個人再生をお考えの方はご相談ください
しかし、債務者が2つ以上の住宅を所有している場合や、自宅に住宅ローン以外の債権を担保するためにも抵当権がつけられている場合などには、この特則が利用できないおそれもあります。
そのため、ご自宅を残しての個人再生ができるかどうか、より具体的な見通しについては、安易に判断せず、個人再生を取り扱っている弁護士に相談して方針を決めるのが良いかと思います。
当法人では、借金にお悩みの方のお力になれるよう、個人再生を含む借金についてのご相談は、原則無料とさせていただいております。
個人再生をお考えの方は、お気軽に当法人の弁護士までご相談ください。